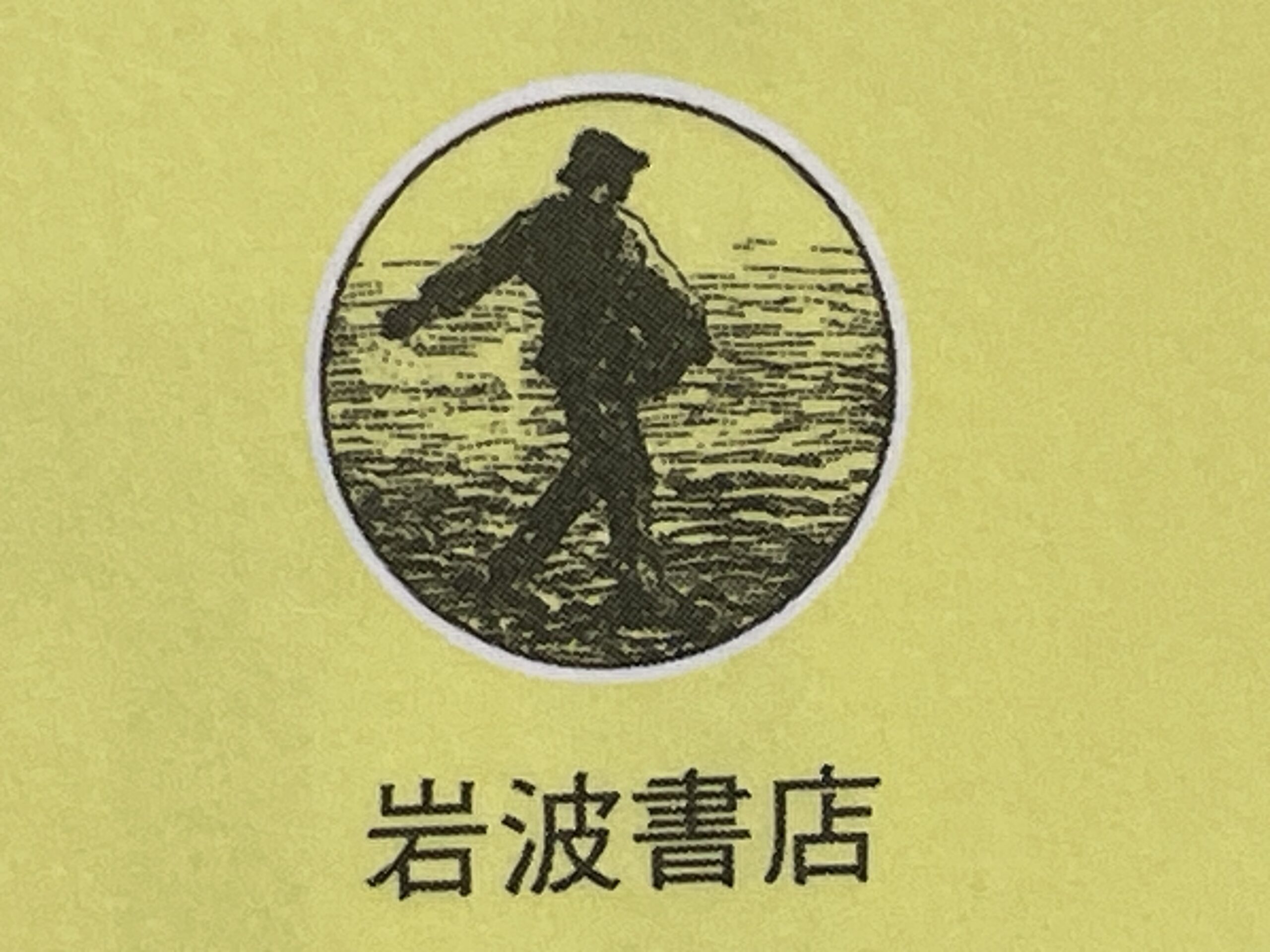こんにちは!皿(sara)です☺️
今回はジャン=フランソワ・ミレー(1814−75、フランス)作『種蒔く人』(1850)という絵画について紹介していきます!
今回『種蒔く人』を選んだきっかけとしましては、最近読んだ本の出版社が岩波書店さんのものだったのですが、その岩波書店さんが社のマークとして採用している絵画こそが『種蒔く人』だったからです。(実際に読んだ本↓)
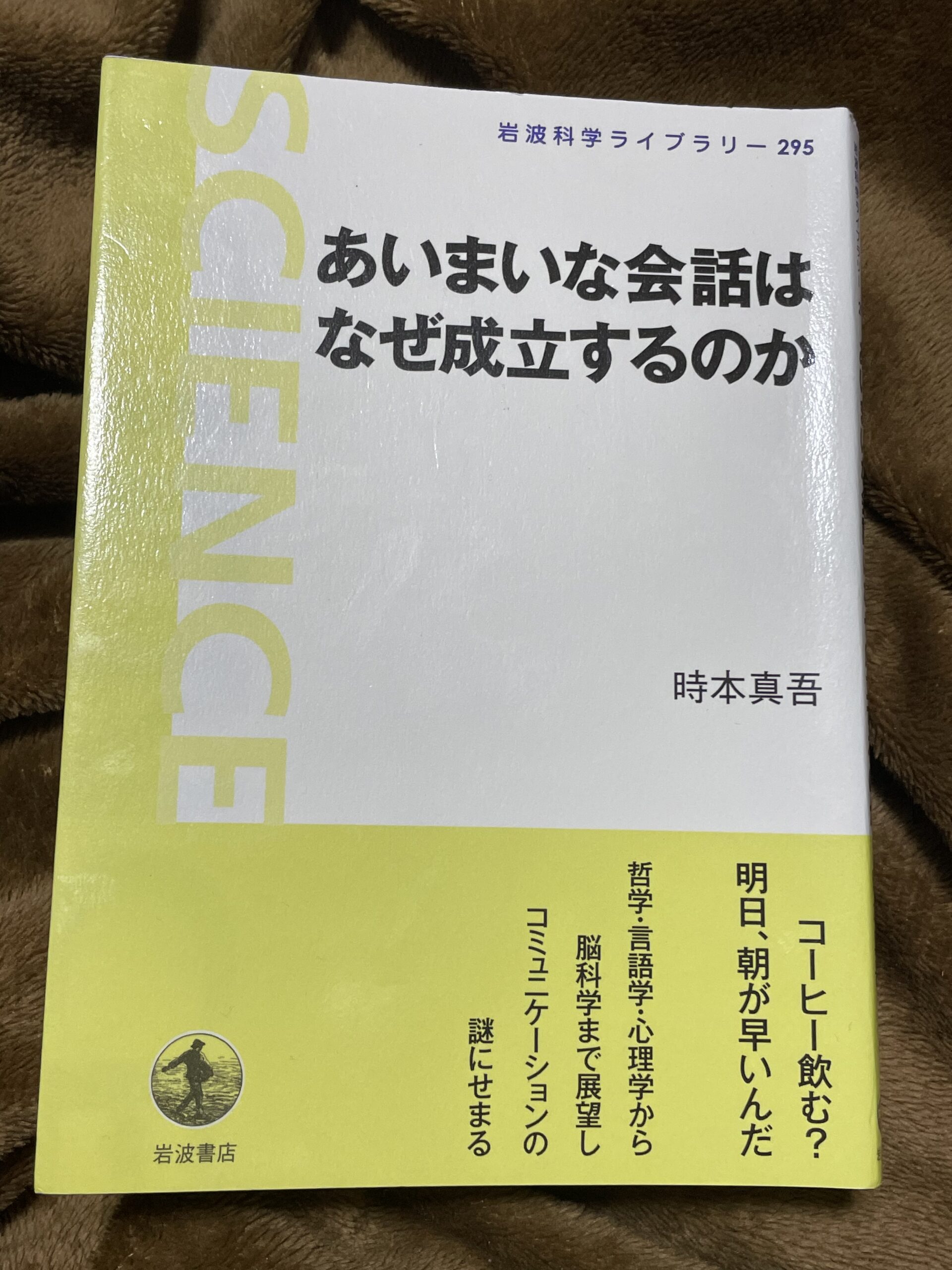
以前から『種蒔く人』が用いられていたことは知っていましたが、今回手に取ったという縁もありましたので取り上げてみようと思った次第です。本文内でもなぜ岩波書店さんが『種蒔く人』を採用したのかという理由についても紹介しておりますので、ぜひ最後まで読んでいただけたらと思います。
それでは、ミレー『種蒔く人』について一緒に学んでいきましょう!
”農民画家”が描き出す農民の気高い姿
ミレーという画家は「農民画家」の別名として通るほど、農民の姿を描くことにおいて右に出るものはいません。有名な他の絵画も以下のとおり↓
『落穂拾い』(1857)
『藁を束ねる人』(1850)
『晩鐘』(1857−59)
いずれの絵画からも、農耕の情景からは静謐、清貧、一方で農民の心の強さのようなものが厳かに伝わってくるようです。しかし、ミレーは初めから農耕の情景を描くことをしていたわけではありません。
元々は生活のため、どちらかというと優美な絵画を描いていました。「女の胸と尻を描く専門家」とまで言われていたそうです。しかし一念発起、産業革命により発展と同時に様々な社会的問題も頻出していた俗世から簡素な田舎に理想郷を求め、”バルビゾン”というフランスの農村行きを決意しました。ミレー同様の思いを抱き、バルビゾンに集った画家たち農民をそのまま「バルビゾン派」と言います。(場合によっては同時期の「写実主義(情景、状況を時に無慈悲でもありのまま伝える)」に含まれますが、少し異なります。)
人間、新しいものや派手なものについ興味が向いてしまうものですが、それに慣れてしまえばまた他の新しいもの、より派手なものを欲するものです。しかし、ずっとそれではいささか「落ち着きがない」「大人しくない」。今あるものでも十分に満足し、感謝できること。そんな平穏な状態こそ、本当に「心が充実している」と言えるのではないでしょうか。
ミレーが生きていた産業革命の時代も、近代化という”陽”が進む一方で「公害」「失業者」などあらゆる”陰”も生まれていました。
「新たなものを求めるが故に今あるものを蔑ろにしていないか」
「社会で成功を追いすぎて苦しく生き続けるくらいなら田舎の自然風景立ち返っても良いのではないか」
ミレーの絵画からは、ただの農耕風景を超越した”ノスタルジー”、”一旦立ち止まってゆっくり考えることの大事さ”のようなものを感じます。
後世の秀才たちから尊敬される画家
『種蒔く人』(↑)は、1850年にサロン(フランスで行われる展覧会)で出品されたところ「農民、農耕の厳しさと強かさ、崇高さ」を表しているとされ、ミレーという画家を一躍有名にした作品になります。
しかしその描写力ゆえ、産業革命当時の権力者、政治家に「現状を批判する反抗的な作品」だと捉えられたことで議論にまでなってしまいました。
ミレーの『種蒔く人』(1850)というと、『ひまわり』で有名なフィンセント・ファン・ゴッホ(1853−90)によって『種蒔く人』(1888)という絵画が作成されていますが、これはゴッホがミレーを尊敬していたためのアレンジと言えます↓
また、上で紹介した『晩鐘』という絵画はサルバドール・ダリ(1904−89)によってアレンジされた作品がいくつか発表されています(そのうちのひとつ↓)
引用:Archeological Reminiscence of Millet’s ‘Angelus’, 1933 by Salvador Dali – Salvador Dali Paintings
ゴッホもダリも、美術史において重鎮も重鎮ですが、そんな2人からも尊敬を受け、さらに各々の解釈によってまた別の作品が作成されたことは、ミレーという画家の画力、表現力、物語性が優れていたことの証左だと言えます。
重鎮たちのアレンジは後付けの魅力ではありますが、後世に多大な影響を与えたという歴史を感じられることも『種蒔く人』の魅力の一つと言えます。
「学ぶ」は元々「真似ぶ」からきているといいます。どんな勉強や練習も、自分より秀でている人の真似をし、吸収することから始まります。重鎮たちがそうしたように、常に人を真似、教わるという謙虚な姿勢を、『種蒔く人』は見る度に意識させてくれる作品にも思われます。
岩波書店が『種蒔く人』をマークに採用している理由
さて冒頭で紹介しました、岩波書店さんは何故『種蒔く人』を採用したのかということですが、サイトにて説明されていましたので引用して紹介します。
創業者岩波茂雄はミレーの種まきの絵をかりて岩波書店のマークとしました.茂雄は長野県諏訪の篤農家の出身で,「労働は神聖である」との考えを強く持ち,晴耕雨読の田園生活を好み,詩人ワーズワースの「低く暮し,高く思う」を社の精神としたいとの理念から選びました.
引用:種まく人」のマークについて – 岩波書店
まさに『種蒔く人』は岩波書店さんの理念にピッタリの作品に思えます。絵画全般に言えることですが、そこにあるのは1枚の絵に過ぎません。しかし、そこから読み取る描写や画家のメッセージ、そして自らが主体的に見ることにより思い起こされる、日々の生活や人生において大切にしたいことや感情などを表現できるのが、絵画をはじめとした美術作品の存在意義であると、私は思います。
当ブログの目標の1つは、「読んでくださった方に絵画作品をインテリアに取り入れてもらい、心を豊かにしたい」というものです。部屋に飾る絵画はただおしゃれなだけではなく、岩波書店さんがそうしているように、目に入るたびに「自分は何を大切にしたいか」を思い出させてくれるようなきっかけであれば、より彩りをもたらしてくれるように思えます。
あなたも、自分が大切にしたいことを表現している絵画を見つけ、それを飾ってみませんか。
おわりに〜こんな人におすすめ〜
絵画を知るほどその魅力は増しますが、しかし絵画を最初に見た瞬間に起きた「あ、この絵良いな」という言語化できない”好き”も同じくらい大事な気持ちだと思うので、「ただ好き」という選び方ももちろん大賛成です☺️
以上でジャン=フランソワ・ミレー作『種蒔く人』の紹介を終わります。いかがでしたでしょうか。
最後の最後でとても大事なことをお伝えしますが、何とこの『種蒔く人』、山梨県立美術館に常設されているんです!!私も知った時はびっくりしました。本文中で1850年のサロンに出品され、ミレーの名を知らしめたとお伝えしましたが、その作品が日本に常設されているだなんて、すごいことですね。他にも多数のミレー作品を所蔵していることから「ミレー館」なるものまであるそうです。すごい。。
ただ『種蒔く人』、実は2点作成されており、もう1つはボストン美術館に所蔵されているのですが、山梨県のものとどちらがサロンに出品された絵画なのかはわからないそうです。そんなことあるんですね!😳
ミレーの人生を変えた出世作かどうかは定かではありませんが、いつか足を運んでみて、ゆっくりじっくりと楽しんでみたいと思います。その時はぜひ、山梨の美味しいものや美しい景色も合わせて楽しめたらなお良い思い出に残りそうですね!
「”いつか”なんて言っていたらいつまでも行動しないんだからちゃんと計画立てなさい」という心のお怒りの声を聞き流しつつ、ここまで読んでくださって、本当にありがとうございました!